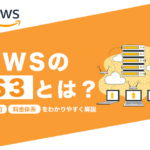老朽化したサーバーを放置するリスクとは?深刻なリスクと今すぐすべき対策を徹底解説

近年、企業活動のあらゆる場面においてITインフラの重要性が増しています。販売管理、在庫管理、顧客情報の蓄積、さらには社内コミュニケーションまで、多くの業務がサーバーを基盤として成り立っています。そのため、サーバーのトラブルや停止は、業務全体に甚大な影響を与える可能性があります。
ところが、実際の現場では「まだ動いているから問題ない」「予算の都合で今は買い替えられない」といった理由で、老朽化したサーバーを使い続けているケースも少なくありません。一見するとコストを抑えているように見えますが、放置された古いサーバーは、実は企業にとって大きなリスクとなり得るのです。
「老朽化したサーバーを放置することの何が問題なのか?」
「どのようなリスクが現実に起きうるのか?」
「どうすればリスクを最小限に抑えられるのか?」
本記事では、これらの疑問に答えながら、老朽化したサーバーがもたらすリスクと、企業がとるべき対策についてわかりやすく解説していきます。
【関連記事】
👉オンプレミスのサーバーが古くなったらどうする?AWS移行の選択肢
第1章:老朽化したサーバーの具体的な問題点
ハードウェアの故障リスクの増加
サーバーは24時間365日稼働し続ける機器です。長期間にわたって稼働させると、ハードディスク、電源ユニット、冷却ファン、メモリなどの物理部品が劣化し、故障する可能性が高くなります。特にハードディスクは消耗品であり、稼働から5年を超えると故障率が急激に上がるというデータもあります。
一部の部品が故障しただけでも、サーバー全体が停止し、業務に多大な影響を及ぼす可能性があります。
メーカーサポートの終了
ハードウェアベンダーやOSベンダーは、製品ごとにサポート期限(End of Support)を定めています。期限を過ぎると、修理対応やパーツ提供、ソフトウェアの更新・サポートが受けられなくなります。
サポートが終了してしまうと、何か問題が発生した際に、迅速な対応ができず、復旧に時間がかかるだけでなく、場合によっては復旧不能という事態も起こりえます。
部品調達の困難さ
古いサーバーになるほど、必要な部品が市場に出回っていないことが多く、万が一の際に交換用パーツが手に入らないことがあります。中古部品に頼るケースもありますが、信頼性の問題があり、安定稼働を保証できません。
また、在庫切れや入荷待ちにより、部品の調達に数週間以上かかるケースもあるため、業務停止期間が長引くリスクも増大します。
性能の低下とシステム全体への影響
サーバーの処理能力は年々進化しています。古いサーバーを使い続けていると、最新の業務アプリケーションやシステムに対応できない、処理が遅い、ユーザー数が増えるとパフォーマンスが劣化するなどの問題が顕在化します。
これにより、従業員の作業効率が下がり、生産性の低下にもつながります。さらに、新しいソフトウェアとの互換性がなく、アップグレードができないといった問題も起こります。
第2章:セキュリティ上のリスク
サーバーの老朽化は、ハードウェア的な問題だけでなく、セキュリティ上の深刻なリスクも引き起こします。特にサイバー攻撃が高度化・巧妙化している現在において、古いサーバーは格好の標的となり得ます。この章では、老朽化がセキュリティに与える影響について詳しく解説します。
OSやファームウェアのアップデートが不可能に
古いサーバーでは、搭載されているOSやファームウェアのバージョンが古いため、最新のセキュリティアップデートが提供されていない、あるいは適用できないケースが多くあります。これにより、新たに発見された脆弱性に対して無防備な状態が続きます。
たとえば、Windows Server 2008やCentOS 6など、すでにサポートが終了しているOSを使い続けている企業は少なくありません。これらは今後、新たな脆弱性が見つかっても、修正されることがありません。
セキュリティパッチが提供されない脆弱性
ソフトウェアにおける「脆弱性(ぜいじゃくせい)」とは、悪意ある攻撃者に悪用される可能性のある弱点のことです。通常、ベンダーは脆弱性を発見するとパッチ(修正プログラム)を配布して対処しますが、サポートが終了したシステムにはパッチが提供されません。
つまり、既知の脆弱性をそのままにした「穴だらけのシステム」をインターネット上にさらしている状態となり、リスクは極めて高くなります。
サイバー攻撃の格好の標的に
サイバー攻撃者は、自動的に脆弱なシステムをスキャンして攻撃対象を探しています。サポート切れのOSや古いWebサーバーは、その特定の脆弱性を突く攻撃ツールが出回っていることもあり、狙われやすいのです。
万が一、攻撃を受けて情報漏えいなどのインシデントが発生すれば、企業の信用は大きく損なわれ、顧客離れや損害賠償など深刻な影響を受ける可能性があります。特に個人情報や機密データを扱う業種では、致命的な損失を招く恐れがあります。
第3章:運用コストの増加
老朽化したサーバーを使い続けることは、一見すると「新たな投資をしない分、コストを削減している」と感じられるかもしれません。しかし実際には、目に見えにくい「隠れた運用コスト」が確実に増加しており、長期的に見ればむしろ非効率です。この章では、老朽サーバーが引き起こすコスト面での問題に焦点を当てます。
メンテナンスの手間とコスト
老朽化したサーバーは故障やトラブルが頻発しやすくなり、それに対応するためのメンテナンス作業が増加します。保守担当者やIT部門のスタッフは、問題発生のたびに原因調査や修復対応に追われることになります。
これにより、本来の業務(新システムの導入やセキュリティ対策など)に割くべき時間が奪われ、結果として全体の業務効率が落ちてしまいます。また、外部の保守業者に依頼する場合は、そのたびに高額な修理費や出張費が発生することもあります。
トラブル対応による人的リソースの消費
トラブルが発生した場合、IT部門だけでなく、業務部門や管理職まで巻き込むことになります。例えば、サーバーの障害でシステムが使えなくなれば、現場の従業員の業務が止まり、上長への報告や顧客対応など、社内全体に広がる負担が発生します。
これは、直接的な金銭的コストではないものの、「人件費」という形でじわじわと経営資源を圧迫していきます。
消費電力と冷却コストの増加
古いサーバーは省電力性能が低く、同等の処理を行う場合でも多くの電力を消費します。また、発熱量も大きいため、サーバールームの空調(冷却)の負荷が高まり、電気代も増加します。
例えば、最新の仮想化サーバーやクラウド基盤と比較すると、古い物理サーバーは同じ性能を出すために2倍以上の電力を必要とすることもあり、これは無視できない固定費の増加につながります。
第4章:事業継続性への影響
企業にとって、サーバーの停止は単なる「機械の故障」ではなく、「事業の停止」に直結する重大な問題です。特に、業務の大部分がITシステムに依存している現代では、老朽化したサーバーの障害が引き起こす影響は甚大です。この章では、事業継続性(Business Continuity)という観点から、そのリスクを考えていきます。
突然のダウンによる業務停止
老朽化したサーバーでは、予告なしに障害が発生することが珍しくありません。特にディスク障害や電源トラブルは突発的に起きやすく、しかも復旧に時間がかかる傾向があります。
業務システムや顧客管理システムなどの中核的なサービスが停止すると、営業活動や社内オペレーションに多大な支障が出ます。たとえば、ECサイトの運営企業がサーバーダウンにより数時間注文処理ができなければ、直接的な売上損失が発生し、機会損失も大きくなります。
顧客や取引先への信頼低下
障害やデータ損失が発生すると、企業の信頼性が問われます。「あの会社のシステムはよく止まる」と思われれば、取引先や顧客が離れていく可能性があります。特にBtoBビジネスでは、システムの安定性は信用の一部として重視される傾向にあり、1度の大きな障害でもビジネスチャンスを失いかねません。
また、システム障害がメディアやSNSで拡散されると、企業イメージにまで悪影響が及ぶこともあります。
復旧にかかる時間とコスト
障害が発生してから業務を完全に再開できるまでには、場合によっては数時間から数日かかることがあります。その間の対応に人手と費用がかかるのはもちろん、復旧作業中の誤操作やさらなる障害リスクも存在します。
また、バックアップ体制が不十分であれば、復旧できないデータが発生する可能性もあり、それは業務にとって致命的な損失となります。
第5章:対策とおすすめのアプローチ
これまで解説してきたように、老朽化したサーバーには多くのリスクが潜んでおり、放置することで企業に大きな損害をもたらしかねません。ここでは、そうしたリスクを未然に防ぎ、安定したITインフラを維持するための具体的な対策とアプローチを紹介します。
定期的なサーバーの棚卸と評価
まず最初に行うべきは、現行サーバー環境の「見える化」です。すべてのサーバーについて以下の項目を把握し、定期的に評価を行う体制を整えることが重要です。
- 稼働年数・保証期限
- 搭載OSとそのサポート状況
- 利用目的と業務重要度
- 性能の使用状況(CPU、メモリ、ディスク)
こうした棚卸しを年1回以上実施することで、リスクの高い機器を早期に発見し、計画的な対応が可能になります。
クラウド移行や仮想化によるリスク軽減
老朽サーバーの代替手段として、クラウドサービスの活用や仮想化環境の導入は非常に有効です。
- クラウド(例:AWS、Azure、Google Cloud)
インフラの管理が不要になり、柔軟な拡張や自動バックアップ、セキュリティ対策が標準で備わっているため、リスクが大幅に軽減されます。 - 仮想化(例:VMware、Hyper-V)
1台の物理サーバー上に複数の仮想サーバーを構築することで、物理機器の台数を減らし、管理効率と可用性を向上させることが可能です。
これらの手法は初期導入に多少のコストがかかるものの、長期的に見ればトータルコストの削減と可用性の向上に大きく貢献します。
計画的なリプレースと予算化の重要性
サーバーは「壊れてから交換する」のではなく、「計画的に更新する」ことが理想です。多くの企業では、5年程度を目安にリプレースを検討するのが一般的です。
リプレース計画を事前に立て、年度ごとに必要な予算を割り当てておくことで、「急な故障で大きな出費が発生する」といったリスクを回避できます。特に中小企業では、IT投資が後回しにされがちですが、業務基盤としてのITの重要性を社内全体で再認識し、優先順位を上げることが必要です。
まとめ
老朽化したサーバーを放置することは、企業のITインフラ全体に深刻なリスクをもたらす行為です。動いているように見えても、内部では劣化が進行し、ハードウェア故障、セキュリティ脆弱性、業務停止リスク、コスト増大など、さまざまな問題が静かに積み上がっています。
多くの企業が「まだ使えるから」「予算がないから」と先延ばしにしがちですが、**突発的なトラブルは予告なしにやってきます。**特にセキュリティに関しては、1回の情報漏えいが信用を失墜させ、回復に長い時間と多大なコストがかかることもあります。
こうしたリスクを避けるためには、以下の3つが特に重要です:
- 現状のサーバー環境を正確に把握し、定期的に評価すること
- クラウドや仮想化など、柔軟で安全なインフラへの移行を検討すること
- サーバーのリプレースを計画的に行い、予算化しておくこと
ITインフラは、企業活動の“土台”です。老朽化したサーバーを「使えるうちは使う」のではなく、「必要な時期に更新する」という予防的な対応が、安定経営と将来の成長を支える基盤となります。
AWSならシースリーインデックス
そのサーバ、もう限界かも?
古いオンプレミスサーバーを使い続けるリスク、見過ごしていませんか?突然の停止や保守コストの増大を防ぐために、今こそAWSへの移行をご検討ください。初期費用も抑えられます。